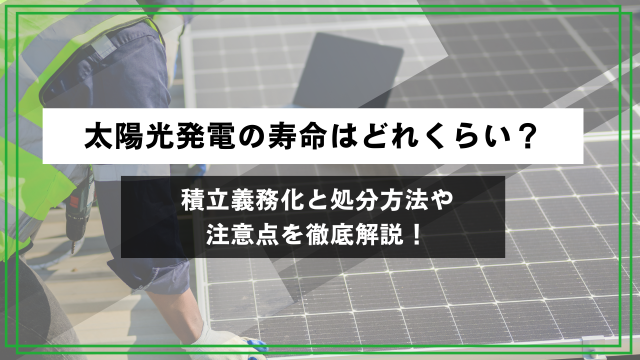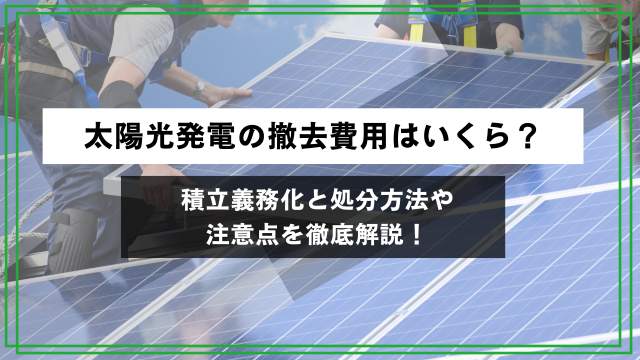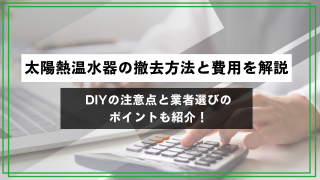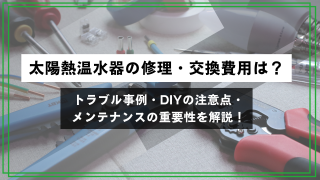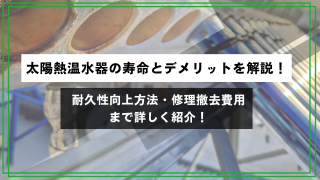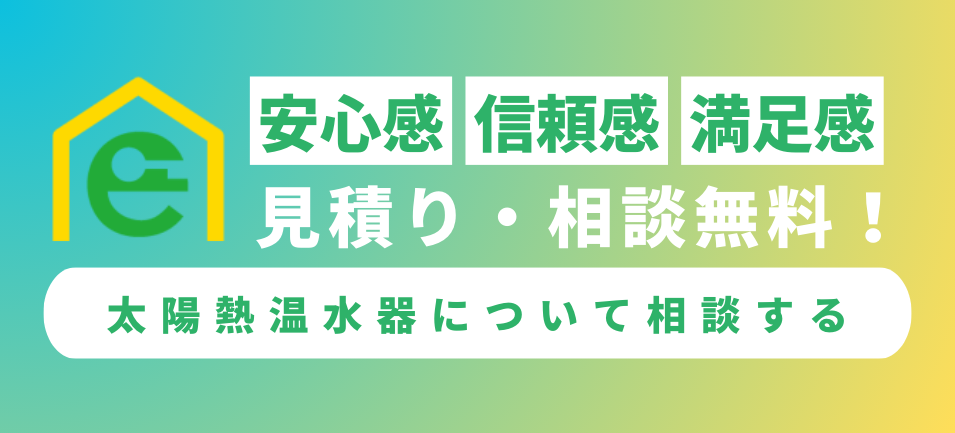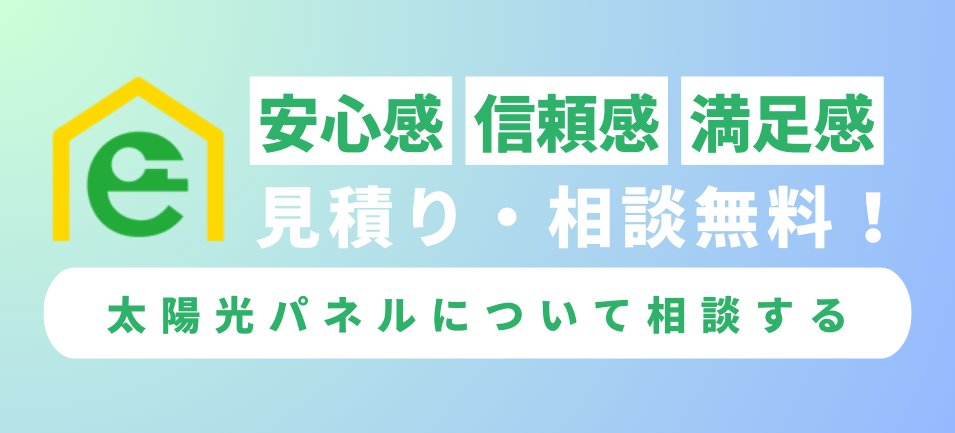太陽光発電はクリーンなエネルギーとして広く普及していますが、設置後に「音が気になる」と感じる方も少なくありません。
特にパワーコンディショナー(パワコン)から発生する高周波音やモスキート音は、若年層や聴覚が敏感な方にとって不快に感じられるケースもあります。
この記事では、太陽光発電システムにまつわる騒音トラブルの原因や対策、防音の工夫、そして静音性に配慮したパワコンの選び方について解説します。設置済みの方も、これから導入を検討する方も、騒音リスクを理解し、快適な使用環境を整えるための参考にしてください。

太陽光発電システムから発生する騒音の原因とは
太陽光発電は基本的に静かな設備ですが、稼働中にわずかな音が発生することがあります。
特に住宅密集地や静かな環境に設置された場合、音に敏感な方や近隣住民にとって、「予想外に気になる音」として騒音トラブルにつながるケースも少なくありません。
騒音の主な発生源は、パワーコンディショナー(パワコン)です。また、機器内部から出る高周波音(いわゆるモスキート音)が気になるという声もあります。
モスキート音と高周波ノイズの正体
モスキート音とは、主に10代〜20代の若年層が聞き取れる高周波音のことです。パワコンが電気を変換する際に内部部品が微細な振動を起こし、「キーン」や「蚊の羽音」のように聞こえることがあります。
この音は個人差が大きく、まったく気にならない人もいれば、耳障りで日常生活に支障をきたすレベルで感じる人もいます。特に図書館のような静かな環境や寝室に近い設置場所では注意が必要です。
モスキート音は電気の変換時に発生するノイズの一種であり、経年劣化や設置環境によって音の感じ方が変わる可能性もあります。
パワーコンディショナー(パワコン)の稼働音
パワコンは、太陽光パネルで発電した直流電力を、家庭で使える交流電力に変換する装置です。
この変換作業に伴い、内部のファンや部品が動作し、「ブーン」や「ジー」といった機械音が発生することがあります。
特に屋内設置型のパワコンは、音が壁や床に反響しやすいため注意が必要です。住宅用でも静音性を重視したモデルは増えていますが、機器の設置場所や音の伝わり方次第で、実際の体感は大きく異なることがあります。
パワコンの音が気になる場合は、騒音だけでなく発電性能にも異常がないか確認することが重要です。発電量が低下する原因と対策については【太陽光発電の発電量低下はなぜ起きる?原因と対策をわかりやすく解説】もあわせてご確認ください。
騒音を感じやすい人と環境の特徴
太陽光発電システムの騒音は、大音量ではなくても、人によっては強く不快に感じられることがあります。
特にモスキート音やファンの駆動音は、聴覚の感度や生活環境によって「気になる」「気にならない」の差が大きいのが特徴です。
音を「不快」と感じやすい条件とは
音の感受性には個人差があり、特に以下のような人は高周波音や機械音に敏感な傾向があります。
- 聴力が鋭い10代〜30代の若年層
- 日頃から静かな環境に慣れている人
- 神経質な性格傾向や音に対するストレス耐性が低い人
- 在宅ワークや夜勤明けで日中に静けさを求める人
また、音の種類も関係しています。継続的に鳴る「ジー」「キーン」といった音は、断続的な音よりも精神的に負担を感じやすいと言われています。
一般住宅と産業用での違い
住宅用の太陽光発電では、近隣との距離が近く、屋内にも音が伝わりやすい環境にあるため、より配慮が必要です。一方、産業用の大型システムでは屋外に設置されるケースが多く、直接人が近づく機会が少ないことから、騒音が問題になることは比較的少ない傾向にあります。
ただし、屋外に設置されたパワコンであっても、近隣住宅と距離が近ければ騒音苦情の対象となる可能性があります。住宅地での導入時は、「どこに設置するか」が騒音リスクを大きく左右する点を理解しておくことが重要です。

太陽光発電の騒音トラブルを防ぐ方法
騒音トラブルは、設置前の配慮や設置後の工夫によって防げる可能性が高いものです。実際に音が発生するパワーコンディショナーの特徴を理解し、対策を事前に講じることが、快適な運用と近隣との良好な関係を維持するカギとなります。
パワコンの設置場所を工夫する
騒音を最小限に抑えるには、パワコンの設置場所選びが非常に重要です。室内設置タイプの場合は、寝室やリビングなどの生活空間から遠ざけることで、音のストレスを減らせます。
屋外設置タイプでも、隣家の窓や自宅の居住スペースに近い場所を避けることで、騒音トラブルのリスクを軽減できます。
設置場所を検討する際には、以下のような点に注意しましょう。
- 壁の反響や床の振動が伝わりやすい場所を避ける
- 直接音が届きやすい向き(開口部の方向)を調整する
- できるだけ建物の外壁や物置などの遮音になる構造物のそばに設置する
工事業者によっては、騒音を考慮した配置提案をしてくれる場合もあるため、事前に相談することをおすすめします。
防音材・防音壁を活用する
すでに設置している場合や、どうしても静かな場所に設置できない場合は、後付けの防音対策も有効です。パワコン周辺に防音パネルや吸音材を設置することで、音の広がりを抑えることができます。
ただし、防音材の使用に際しては以下の点に注意が必要です。
- 通気性や排熱性を確保する(パワコンの過熱を防ぐため)
- 完全に囲い込まず、あくまで反響を抑える設計にとどめる
- 専門業者に相談して安全性を担保することが望ましい
また、防音ボックスのような市販品もありますが、製品によってはパワコンのサイズや機種に適合しないことがあるため、選定時は寸法や放熱性能をしっかり確認することが重要です。
静音性に優れたパワコンを選ぶポイント
太陽光発電システムの導入時、パワコンの性能だけでなく“静音性”にも注目することが、後の騒音トラブル回避につながります。 現在は、住宅用に設計された静音モデルのパワコンも各メーカーから販売されており、導入時の選定が重要な対策の一つです。
メーカー別に見る静音モデルの特徴
主要なパワコンメーカーでは、住宅環境での使用を想定した静音モデルがラインアップされています。ファンレス設計やノイズを抑える回路構成など、製品によって静音への取り組み方には違いがあります。
例としては以下のような特徴があります。
- ファンレス設計:可動音の発生を抑えることで、稼働音が極めて静かになる
- 高周波ノイズ抑制技術:回路設計でモスキート音の発生を軽減
- 自動モード制御:夜間や低負荷時に動作音を抑える制御が可能なモデルも
製品仕様書には「運転音」や「騒音レベル(dB)」が記載されていることも多いため、比較検討の際にはスペックシートに記載された数値を確認することが大切です。
購入・交換時のチェックポイント
新設だけでなく、既存システムからのパワコン交換(リプレース)時も、静音性に配慮した製品選びが重要です。特に、10年以上前のモデルから交換する場合、技術進化により静音性が格段に向上しているケースもあります。
選ぶ際に意識すべきポイントは次の通りです。
- 製品の音に関する口コミやレビューを確認する
- 住宅密集地や集合住宅では、静音モデルを優先的に検討する
- 販売業者や施工業者に「騒音リスクを考慮した提案」が可能か確認する
音に関して不安がある場合は、実際に製品の運転音を確認できるショールームや設置事例を問い合わせるのも有効です。後悔しないためには、価格や出力性能だけでなく、「聞こえ方」にも配慮した選定が必要です。
太陽光発電の騒音が気になるときの相談先
太陽光発電システムの騒音に悩まされている場合、我慢せずに早めに相談・対応することが重要です。音の感じ方には個人差があるため、放置するとストレスの蓄積や近隣トラブルにつながる可能性もあります。対応は状況に応じて段階的に進めましょう。
自治体・メーカー・販売業者の対応
まず相談先として考えられるのは、販売業者や施工業者です。設置した業者であれば、設置状況やパワコンの機種を把握しているため、設置ミスや不具合の可能性を含めて点検対応が可能です。
また、製造メーカーに直接問い合わせることで、製品仕様や動作音の範囲内かどうか、交換対象となるかなどの確認も行えます。
それでも解決しない場合や、近隣住民から苦情が寄せられている場合は、自治体の生活環境窓口や消費生活センターへ相談することも検討しましょう。対応の履歴を残しておくことで、万が一の法的トラブルに備えることもできます。
苦情が来る前に取るべき行動とは
近隣とのトラブルを未然に防ぐには、導入前に配慮することがもっとも効果的な対策です。設置場所や機種の選定はもちろん、導入時に簡単な説明や一言挨拶をしておくことで、関係性を良好に保てる可能性が高まります。
設置後に「音が気になる」という声が出た場合も、早期に調査・対応を申し出る姿勢が信頼につながります。 問題を軽視せず、事実確認と改善策の提示を速やかに行うことが、円満な対応の第一歩です。
騒音やその他の異常を未然に防ぐには、定期点検が不可欠です。2020年代以降、住宅用太陽光発電ではメンテナンスの義務化も進められており、点検内容や費用について事前に知っておくことをおすすめします。
メンテナンスの義務化については【住宅用太陽光発電のメンテナンスが義務化!必要な点検内容と費用を詳しく解説】もあわせてご確認ください。
まとめ
太陽光発電システムは基本的に静音性の高い設備ですが、パワーコンディショナーから発生する高周波音やモスキート音が原因で、思わぬ騒音トラブルにつながるケースもあります。 特に住宅密集地や静かな環境では、音に対する感受性が高い人にとって不快に感じられることもあるため、設置段階からの配慮が欠かせません。
設置場所の工夫、防音対策、静音性に優れたパワコンの選定などを通じて、騒音リスクを軽減することが可能です。 さらに、気になる場合は販売業者やメーカーに早めに相談し、必要に応じて点検や交換を検討することが大切です。
太陽光発電を安心して利用するためには、発電効率や費用だけでなく、「音」の問題にも目を向けることが重要です。静かで快適な再生可能エネルギーのある暮らしを実現するために、設置前後の対策と配慮をしっかりと行いましょう。